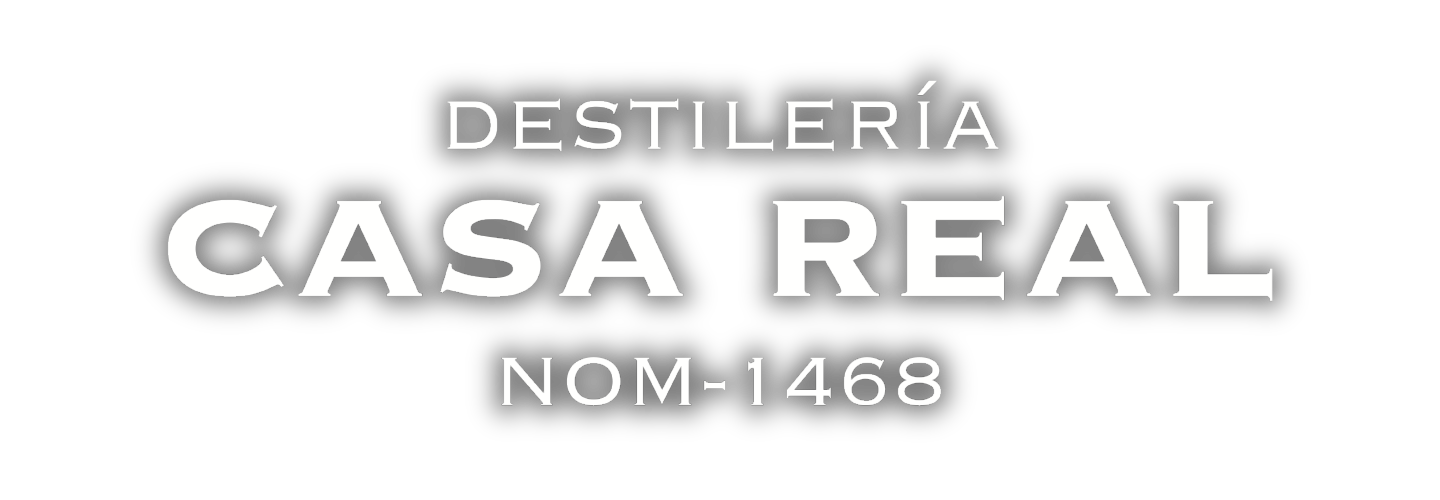How
Casa Real
Came to Japan
蒸留所で初めてCasa Real Colibriを口にしてから、実際に日本に輸入できるようになるまでに約3年を費やしました。
「なぜそこまでして?」と思われるかもしれません。
その理由と、輸入に至るまでの道のりを紐解いていきます。
Casa real Colibriを輸入した理由
その道のり
テキーラとの出会い
学生時代にクラブやダーツバーで一気したことはありましたが、私(代表 片山)が初めてテキーラを本当に美味しいと感じたのは、旭川にあった「ラムヘッド」というラムとテキーラの専門バーでした。雪国の旭川には不思議に思える南国の空気をまとったその店に、社会人2年目で転勤したばかりの私は自然と惹きつけられました。
それまで多少はラムの知識があるつもりでいましたが、店に並ぶのは見たことのないボトルばかり。独特な雰囲気を持つドレッドヘアのマスターに圧倒され、知識をひけらかすのではなく、素直に教えを乞うことにしました。最初はラムを中心に楽しんでいましたが、マスターの勧めで一度だけ口にしたテキーラが衝撃を与えてくれたのです。苦手だと思い込んでいたテキーラが、こんなにも奥深く美味しいお酒だと気づいた瞬間でした。その後、約3年間旭川に滞在した私は、通い続ける中でマスターから多くを学び、少しずつテキーラの世界にのめり込んでいきました。この出会いこそが、後に私がテキーラを輸入しようと決意する大きなきっかけとなったのです。


テキーラマエストロ取得と
テキーラ専門ウェブサイト
その後、旭川を離れ、札幌、東京へと引っ越しました。その後もテキーラは好きだったのですが、Don Julio(ドン・フリオ)やHerradura(エラドゥーラ)という大手蒸留所のテキーラを、特にこだわりなく家で何となく飲むような日常を過ごしていました。
プライベートでは子供も生まれ、2020年4月コロナ禍に入りました。世の中ではお酒を飲む機会が減り、夜の飲み会時間も減っていました。夜に時間もあるし、昔から好きだったテキーラを改めて勉強したいと思い、以前から興味があったテキーラマエストロという資格の取得をしようと考えました。ただ、せっかく勉強するなら、何かアウトプットしないと見につかないのではないかと思い、自身でテキーラの専門ウェブサイトの作成を思いつきました。テキーラマエストロの講義を受けながら、記事をどんどん作成、取得後も自分でテキーラを買い漁り、テキーラの知識と体験を深化せていくのです。
それまではメーカー主導のテキーラ情報、メーカーから広告をもらうようなサイトが中心だったため、テキーラの丁寧な解説とブランドレビューにより、1年程度で日本におけるテキーラの専門ウェブサイトとしては最も見られるサイトとなったのです。
Casa Realへの歩みを導いたブランド -LALO-
私がCasa Realを輸入するきっかけとなったブランド、LALOとのつながりを振り返ります。
テキーラは好きで楽しんでいましたが、改めてテキーラを学ぶ中で、大手の大量生産ブランドでは感じられない、自然で深い味わいを求めるようになりました。
そんな折、テキーラ道場の前田さんから、LALOという新しいブランドの存在を教えてもらいました。LALOは、人気ブランドを創った人物の孫が立ち上げたもので、自身の名前を冠したブランドです。ボトルのデザインや哲学には祖父のこだわりが色濃く反映されており、大手ブランドへのアンチテーゼとも言える個性が感じられました。
実際に個人輸入して試飲すると、香りは華やかでアガベの自然な甘さがしっかりと感じられ、大手ブランドでありがちな人工的な甘さは一切ありませんでした。この体験を通じて、「このブランドを日本に紹介したい」という強い思いが芽生れ、Casa Real Tequilaの輸入への道が始まったのです。
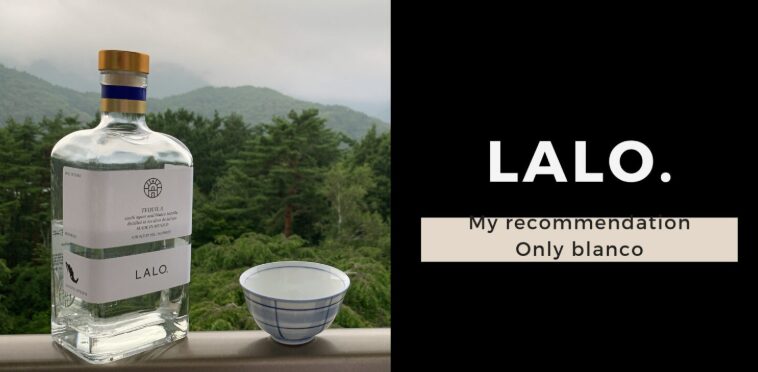
渡墨 -Casa Realに出会うまで-
テキーラの知識を深めるにつれ、メキシコの蒸留所の雰囲気を肌で感じ、製造現場を見たいという思いが強くなりました。2023年初頭、本業の休みを利用してメキシコ訪問を決意。LaloさんにDMを送り、日本での取扱について打診しましたが、米国での売上が好調なこともあり、日本への輸出には積極的でない状況でした。
それでも蒸留所自体を訪れたい思いは変わらず、アテンドを依頼していたアミさんに、LALOを手掛けるDestilería Casa Real(Casa Real蒸留所)へのアポイントをお願いしました。※Laloさん自身は蒸留所で直接製造しているわけではなく、OEM方式でLALOを作っています。
初めは蒸留所側も、日本向けの輸出銘柄がないことから難色を示しましたが、日本におけるテキーラ情報発信の実績を評価してくれ、将来的な日本輸出を見越して見学を許可してくれました。
一週間かけて様々な一流の蒸留所を見学した後、最終日にDestilería Casa Realに訪れました。


渡墨 -想像以上の出会い-
蒸留所はLALOの米国でのヒットにより大忙しでしたが、オーナーの娘さんが丁寧に案内してくれました。新しく移転した蒸留所は清潔で美しく、昔ながらの製法を現代的な設備で行うため、アガベの香りが充満していました。
製造工程の最後に、OEMブランドのLALOではなくCasa Realを試飲。正直なところ最初はあまり期待していませんでしたが、一口で衝撃を受けました。華やかな香りと自然なアガベの甘さは、LALO以上に自分好みで、これまで飲んできた数百種類のテキーラとは一線を画す味わいでした。また味わいのなかに、自分自身が大好きな和食に合うのではないかと確信に近い思いをいただきました。本当に美味しいテキーラを日本人に知ってほしいと思っていたので、この味ならば日本の人々もテキーラを本当の意味で味わう機会を増やせるのではないかと確信したのです。
その場で通訳のアミさんを通じて日本での輸入可能性を交渉。熱意に押され、オーナーの娘で営業責任者のエスメラルダさんが前向きに検討してくれることになりました。
日本輸入に向けた3年間
日本に戻ってから、当時付き合いのあった中堅テキーラ輸入会社にCasa Realの取り扱いを打診しました。担当者や同社が運営するバーの責任者に試飲してもらい、美味しさの評価を得ました。その後、約1年かけて輸入契約の調整を行いましたが、協業先の企業が条件変更を求めたため契約を断念しました。
その後、現在Casa Realの輸入を共に行うJ-DOX社と急ピッチで交渉を開始。Destilería Casa Real、J-DOX社、Premium-Tequilaの三社で打ち合わせを重ね、J-DOX社もCasa Realの味に納得したことで、三社による協業が実現しました。
輸入を通じた挑戦と目標
私はこれまでサラリーマンやウェブメディア運営を続けながらも、このテキーラを輸入したいと強く思いました。
日本では長らく「テキーラ=罰ゲーム」というイメージが強く、一部の高級ブランドによって少し改善されてはいますが、まだ食中酒として広く楽しまれているわけではありません。特に若年層は、バーでもダーツバーやシーシャバーなどで飲むことが多く、ネガティブな印象を持ち帰ってしまうことが多いと感じています。
一方、Casa Realを初めて飲んだとき、華やかな香りとアガベの自然な甘みが印象的で、和食との相性も強く感じました。日本で最もお酒が楽しまれる食中の場でテキーラを提供できれば、「テキーラ=罰ゲーム」というイメージを覆し、「美味しいお酒」として体験してもらえる人を増やせると確信しています。
Casa Realは私の中でただの商材ではなく、チャレンジであり、2年半かけて日本に届けることができた我が子のような気持でもあります。このCasa Realをぜひ多くの方に味わっていただき、テキーラって美味しいんだって思っていただくきっかけになればと思っています。